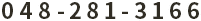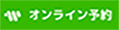2025/03/17
愛猫が「くしゃみをしている」「目やにや鼻水が増えている」「元気がない」といった症状を見たことはありませんか? こうした症状は「猫ヘルペスウイルス感染症(猫ウイルス性鼻気管炎)」の可能性があります。
猫ヘルペスウイルスは非常に感染力が強く、一度感染すると体内にウイルスが潜伏し、何度も再発することがあります。そのため、症状が軽いうちに適切な治療を行い、重症化を防ぐことが重要です。
今回は猫ヘルペスウイルス感染症について、原因や症状、診断方法、治療方法、予防策などを詳しく解説します。

■目次
1.このような症状はありませんか?
2.猫のヘルペスウイルス感染症とは?
3.症状
4.診断方法
5.治療方法
6.感染予防のポイント
7.日常的なケア方法
8.再発予防
9.飼い主様のためのガイド
10.よくある質問(Q&A)
11.まとめ
このような症状はありませんか?
猫ヘルペスウイルス感染症は軽症で済むこともありますが、重症化すると肺炎を引き起こし、命に関わることもあります。早期発見のために、以下の症状をチェックしましょう。
<緊急性の高い症状チェックリスト>
・目の周りがただれている、目やにが多い
・くしゃみや鼻水が止まらない
・食欲がなく、ぐったりしている
・高熱(39.5℃以上)がある
・呼吸が荒い、鼻が詰まって苦しそう
<要受診の判断基準>
軽度のくしゃみや鼻水だけであれば、自宅で様子を見ることもできますが、症状が2〜3日以上続くようであれば、動物病院を受診することをおすすめします。また、食欲が落ちたり元気がなくなったりしている場合は、早めに診察を受けることが大切です。
ほかにも、目やにや涙の量が増え、結膜が赤く腫れているような症状が見られる場合は、そのままにしておくと角膜潰瘍を引き起こす可能性があるため、早めの受診を心がけましょう。
<応急対応の方法>
・目や鼻の汚れは、清潔なガーゼで優しく拭く
・食欲が落ちている場合は、ウェットフードなど食べやすいものを与える
・空気の乾燥を防ぐため、加湿器を使用する
ただし、これらはあくまで応急処置です。症状が悪化する前に早めに動物病院へ連れていきましょう。
猫のヘルペスウイルス感染症とは?
猫ヘルペスウイルス感染症は、猫ウイルス性鼻気管炎(FHV-1)とも呼ばれ、猫風邪の主な原因ウイルスのひとつです。特に子猫や免疫が低下した猫で重症化しやすいのが特徴です。
猫ヘルペスウイルスは、感染した猫のくしゃみ・鼻水・目やにに含まれるウイルスが空気中に拡散し、それを吸い込むことで感染します。また、ウイルスが付着した食器や毛布、飼い主様の手や衣類を介しても感染が広がるため、多頭飼育では注意が必要です。
<感染リスクの高い状況>
・野良猫との接触(外出自由な猫)
・新しく猫を迎え入れたとき
・動物病院やペットホテルの利用後
・多頭飼育環境での感染拡大
症状
【全身症状】
猫ヘルペスウイルス感染症にかかると、全身にさまざまな症状が現れます。特に免疫力の低い子猫や高齢の猫は重症化しやすいため、早めの対応が重要です。
■発熱(39.5℃以上)
猫の平熱は37.5℃〜39.2℃程度ですが、感染すると体温が上昇し、39.5℃以上の高熱が出ることがあります。発熱すると、ぐったりして動かなくなることもあります。
■食欲不振・元気消失
体調が悪くなると食欲が低下し、お気に入りのフードにも興味を示さなくなります。食べる量が極端に減ったり、水も飲まなくなったりした場合は、早めに受診しましょう。
■脱水症状
鼻水や発熱によって水分が失われるため、脱水を引き起こすことがあります。皮膚を軽くつまんで離したときに、すぐに元に戻らない場合は、脱水のサインです。
<重症度の判断基準>
症状の重さによって、緊急度が異なります。
・軽度:くしゃみや鼻水が少し出るが、食欲や元気はある
・中等度:発熱や食欲不振があり、目やにや鼻水が増える
・重度:高熱や呼吸困難、肺炎を伴い、ぐったりしている
<年齢による症状の違い>
年齢によって、症状の現れ方が異なります。
・子猫:免疫が未熟なため、重症化しやすく、肺炎やウイルス血症を引き起こすこともあります。特に生後数か月の子猫は注意が必要です。
・成猫:免疫があるため、軽症で済むことが多いですが、ストレスや体調不良で症状が悪化することもあります。
・老猫:加齢により免疫力が低下しているため、感染すると重症化しやすくなります。早めの治療が重要です。
【呼吸器症状】
猫ヘルペスウイルスは、呼吸器系に強く影響を与えるため、くしゃみや鼻水、鼻づまりといった症状が現れやすくなります。
■くしゃみが頻繁に出る
ウイルスが鼻の粘膜に炎症を引き起こすことで、くしゃみの回数が増えます。最初は軽いくしゃみでも、症状が進行すると頻繁に連続して出るようになります。
■鼻水・鼻づまり
鼻水が透明でサラサラしているうちは軽症ですが、症状が進行すると粘り気のある黄色や緑色の鼻水に変わり、鼻づまりを引き起こします。鼻が詰まると、口呼吸をするようになり、食事がしづらくなることもあります。
<症状の進行段階>
・初期:透明な鼻水が出て、軽いくしゃみをする
・中期:くしゃみの回数が増え、粘り気のある鼻水が出る
・重度:鼻が完全に詰まり、口呼吸になる。呼吸困難の兆候が見られる
<注意すべき変化>
鼻水の色が黄色や緑色に変化した場合は、細菌感染を起こしている可能性があります。また、口を開けて呼吸している場合は、呼吸が苦しくなっている可能性があり、緊急性が高い状態です。速やかに動物病院を受診することが重要です。
【眼症状】
猫ヘルペスウイルス感染症は、目にも強く影響を与えることが特徴のひとつです。放置すると視力障害につながることがあるため、早めの治療が必要です。

■結膜炎(目が充血し、目やにが増える)
目の粘膜が炎症を起こし、赤く腫れることがあります。目やにも増え、べたついた黄色や緑色の目やにが出ることもあります。
■流涙(涙の増加)
目に炎症が起こると、涙の分泌量が増えます。涙で目の周りが濡れてしまい、毛が変色することもあります。
■角膜潰瘍(黒目の傷)
ウイルスによる炎症が悪化すると、角膜に傷がつき、「角膜潰瘍」を引き起こすことがあります。角膜潰瘍になると、目を開けづらくなったり、痛みで瞬きを繰り返したりするのが特徴です。重症化すると、視力低下や失明につながることもあります。
<角膜潰瘍のリスク>
・軽度:目を細める、涙が増える
・中等度:黒目が白く濁る、まぶしそうにする
・重度:角膜が深く傷つき、失明のリスクがある
診断方法
猫ヘルペスウイルス感染症の診断は、症状の観察と検査結果を総合的に判断して行います。
①視診と問診
まずは、くしゃみや鼻水、目やになどの症状の有無を確認します。発症の経緯やワクチン接種歴、多頭飼育の有無なども重要な情報です。
②遺伝子検査(PCR検査)
確定診断には結膜や鼻腔、口腔のぬぐい液を採取し、PCR検査でウイルスを検出します。ただし、検査結果が出るまでに時間がかかるため、症状をもとに治療を始めることもあります。
③一般的な検査
症状が重い場合は、全身状態を把握するために追加で以下の検査を行います。
・血液検査:炎症や脱水の有無を確認します。
・レントゲン検査:肺炎の合併が疑われる場合に実施します。
犬や猫の血液検査、尿検査、糞便検査についてはこちらから
犬や猫の心電図、血圧、レントゲン、エコー検査についてはこちらから
治療方法
猫ヘルペスウイルス感染症はウイルスを完全に排除することが難しいため、対症療法が中心となります。
<基本的な治療方針>
・免疫力を維持し、症状を軽減する
・食欲や水分補給をサポートし、体力を回復させる
<症状別の治療法>
・目の症状(結膜炎・角膜潰瘍):抗ウイルス点眼薬、抗生剤入りの目薬を使用します。
・呼吸器症状(くしゃみ・鼻水):ネブライザー(蒸気吸入)で鼻の通りをよくし、抗生剤を投与することがあります。
・全身症状(発熱・脱水):点滴治療や食欲増進剤を使用して体力を維持します。
<入院が必要なケース>
入院が必要となるケースとして、高熱や重度の脱水が見られ、食欲が全くない場合が挙げられます。このような状態では、自宅での管理が難しく、適切な点滴や治療を受けるために入院が必要になることがあります。
また、肺炎を併発し、呼吸が苦しそうな様子が見られる場合も、迅速な治療が求められるため、早めに動物病院で診察を受け、必要に応じて入院治療を行うことが大切です。
<治療費と保険適用について>
通院での治療費は、1回あたりおよそ5,000円~10,000円程度かかりますが、症状が重く入院が必要になった場合は、治療内容によっては数万円以上の費用がかかることもあります。ペット保険に加入している場合、契約内容によっては治療費の一部が補償されることがあるため、事前に補償の範囲や適用条件を確認しておくと安心です。
感染予防のポイント
前述したとおり、猫ヘルペスウイルス感染症を完全に防ぐ方法はありませんが、ワクチンは発症を抑えたり、症状を軽減したりする効果があります。特に子猫や免疫力の低い猫にとって、ワクチンは重症化を防ぐ重要な手段です。
ワクチン接種の推奨スケジュールは以下の通りです。
・子猫の場合:生後8週、12週、16週で3回接種
・成猫の場合:1年ごとの追加接種
<具体的な予防策>
新しい猫を迎えた際は、先住猫との接触を避けるために1~2週間ほど隔離し、その間に健康状態をしっかり観察することが大切です。また、外出後は手を洗い、衣服を着替えてから猫に触れることで、外から持ち込んだウイルスや細菌の感染リスクを減らせます。さらに、食器やトイレは定期的に洗浄し、常に清潔な状態を保つことで、感染症の予防につながります。
<多頭飼育での注意点>
多頭飼育の環境では、1匹が感染すると他の猫にすぐ広がるため、以下の点に注意しましょう。
・感染した猫は別の部屋で隔離する
・猫同士の食器やトイレは分ける
・くしゃみや鼻水が出ている猫がいたら早めに受診する
日常的なケア方法
猫ヘルペスウイルス感染症は初期症状の見逃しが重症化につながるため、日々の健康チェックが重要です。以下の点を確認しましょう。
・目やにや鼻水が増えていないか
・くしゃみの回数が増えていないか
・食欲や元気があるか
<体調管理>
・食事は栄養バランスの良いフードを与える
・寒暖差に注意し、快適な室温を保つ
・ストレスを減らすため、静かな環境を整える
<環境整備>
・空気清浄機や加湿器を使用し、室内の空気を清潔に保つ
・猫の寝床やトイレを定期的に掃除する
・ウイルスが付着しやすい毛布やタオルはこまめに洗濯する
再発予防
猫ヘルペスウイルスは免疫力が低下すると再発しやすくなるため、季節ごとのケアが大切です。
・春・秋:花粉や気温差で体調を崩しやすいです。室温管理を徹底しましょう。
・夏:暑さで体力が落ちることがあります。水分補給を意識しましょう。
・冬:乾燥で目や鼻の粘膜が弱くなるため、加湿器を活用しましょう。
また、ストレスは免疫力の低下を引き起こす大きな要因となるため、できるだけ猫が安心して過ごせる環境を整えることが大切です。まず、静かで落ち着ける空間を作り、猫がリラックスできる場所を確保しましょう。
さらに、適度な遊びやスキンシップを取り入れることで、安心感を与え、精神的な安定につなげることができます。また、トイレや食器の場所を頻繁に変えてしまうと猫が不安を感じることがあるため、できるだけ一定の場所に保つことが重要です。
<再発時の早期発見ポイント>
・くしゃみや鼻水が増えたら注意
・目やにが増えたり、目をしょぼしょぼさせたりしていないか確認
・元気や食欲が落ちたら早めに受診
飼い主様のためのガイド
<発症時の対応手順>
①目や鼻の汚れを清潔なガーゼで拭き取る
②食事や水を摂取しているか確認する
③症状が悪化する前に動物病院を受診する
<通院時の準備>
・症状の記録(いつから・どの程度か)
・目やにや鼻水の色や状態をチェック
・ワクチン接種歴が分かるものを持参
<自宅でのケアポイント>
・処方された薬を適切に使用する
・療養中の猫がリラックスできる環境を作る
・多頭飼育の場合は他の猫への感染を防ぐため、隔離する
よくある質問(Q&A)
Q1: 猫ヘルペスウイルスは人に感染しますか?
人には感染しません。 しかし、ウイルスが手や衣類に付着し、別の猫に感染を広げる可能性があるため、接触後は手洗いを徹底しましょう。
Q2:完治することはありますか?
ウイルス自体を完全に排除することはできませんが、適切なケアで症状を抑えることが可能です。 免疫が低下すると再発することがあるため、日頃の健康管理が重要です。
Q3:どのくらいで回復しますか?
軽症なら1〜2週間で改善します。 ただし、免疫力が落ちている猫では長引くことがあるため、こまめなケアが必要です。
まとめ
猫ヘルペスウイルス感染症は、一度感染すると体内にウイルスが残り、再発を繰り返す厄介な病気です。特に子猫や免疫力の低い猫は重症化しやすいため、早期の治療と予防が大切です。
ワクチン接種や衛生管理を徹底し、感染のリスクを減らしましょう。愛猫の体調に異変を感じたら、できるだけ早く動物病院を受診することをおすすめします。
■関連する記事はこちらから
健康診断の大切さについて
子犬子猫を迎えたら-健康診断/予防診療編-
犬と猫のワクチン接種|大切な愛犬愛猫を病気から守るための予防医療の重要性について解説します
埼玉県川口市・さいたま市(浦和区)・越谷市を中心に診療を行う
森田動物医療センター
当院の診療案内はこちら